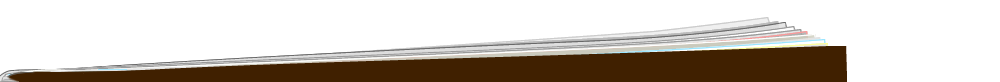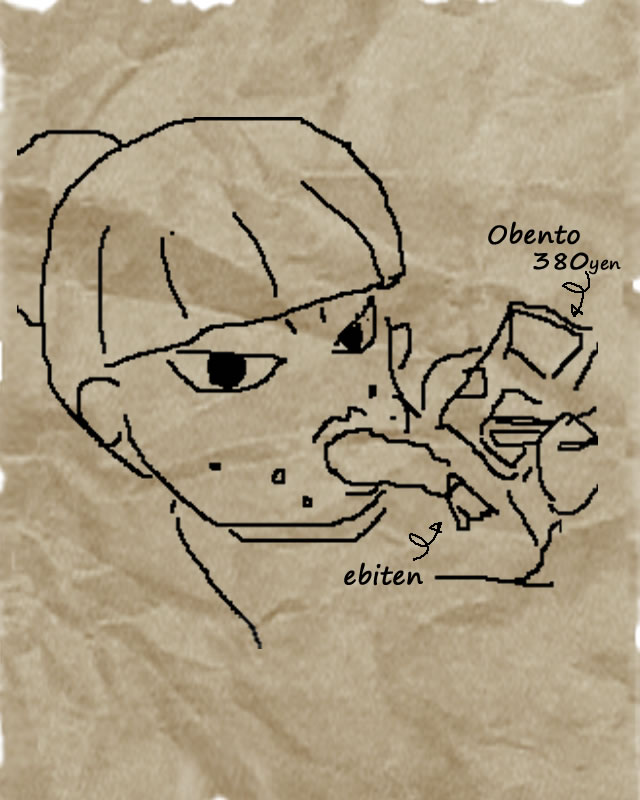導線
最初に勤めた会社は、社員教育はかなり熱心だったと記憶しております。
洋服屋だったんですが、バブルの時で人不足のため、あっと言う間に店長になったり、いろんな作業をしました。
お陰で、その後、どこでどんな仕事をするにも楽でした。
また会社にもちょっと変わった人が多かったんですよ。
でも、当たり前って言えば当たり前の事。
でも、その当たり前って、同じような産業でも企業によって違うんですよね。
例えば、縫製が雑な商品が届いたとき、
最初の会社は『不良品として、他の商品を破っても全部返品しろ』という指示が飛んできました。
何故かっていうと、1つは当然客にとっての不利益=店にとっての不利益という考え
もう1つは、それを許すことによって、出荷側の考えが甘くなり、相手が自分たちに対してまともな仕事をしてこなくなる事を防ぐ為です。
かなり強気なのは、会社や担当者の性質も大きいとは思いますが、勤めていた旅行会社では、この考えが主流でした。
当たり前ですよね、お客様からの苦情をもろに受けるわけなので。
ただ、普段からできるだけ、トラブルにならないようにっていう配慮はあるんですがね。
で、その後、大手のブランドでも働いたんですがね、おかしな商品を不良品扱いにしようとすると
『あなたは、これを不良品っていうのですか?
それを不良品として売らないのが、あなたたちの仕事でしょう?』
みたいな事を言われました。
まぁ、私なので素直に従いませんが。
でも、一理あると言えば一理あるんですよね。
不良品を売るのはヨロシクないけれど、陳列するにしても、接客するにしても、この商品をどうやって売るかを考えるのが、店頭に立つものの役目なので。
因みに、最初の会社は、何でも自分ですることになるので、商品知識やディスプレー、販促の仕方、店のレイアウトなど、いろんな事を教えてくれました。
例えば、種をまいて水をやれば作物が育つわけではないように、品物をそこに並べておけば売れて行くっていうわけでもないんですよね。
少なくとも私が勤めていたような会社では。
すると、商品知識をつけましょう、お客様が見てわかりやすいように表示や演出をしましょう。
ってことに加えて、どうやってお客さまの流れを作るかとか、どうやって売りたい商品までお客さまを結ぶか…って話しになってくるんです。
それが導線。
これができていないと、いくら良い商品を並べたところで、そこまで足を運んでもらえないのです。
けど、こっちが道導を作ったところで、お客さまにその気がないと、そこにたどり着いてくれません。
すると行われるのが、お客さまの流れの研究みたいなものです。
それに合わせて、配置を行うわけです。
商品棚なら、そんな風に配置をすることもできますが、実際にはそう簡単でもない。
たとえば、テナントとしてはいる場合は、どうやっても目につきやすい場所もあれば、つきにくい場所もある。
となると、どうやってその近くまで来てくれる人にアピールするかという話しになります。
それが、販促活動であったり、日頃の接客だったり。
物が売れなくなると、足元見てくる人もいるわけですよ。
買ってあげるみたいな。
逆の場合もありますよ。売ってあげるみたいなの。でも、ちょいと置いといて。
お客様は神様ですとは言いますが、提供する側はお客様の奴隷ではないと思います。
なので、ある意味、お客様が納得してお金を支払われるなら、立場的には対等かと思います。
でも、それとお客様の満足度を上げたり、知って頂くための努力というのはまた別の話。
不必要に媚びる必要はないし、それを許す事が、結局はサービスの質を保つ上にマイナスになることもあります。
と同時に、売り手の気持ちがどうであれ、消費者は自分がお金を払いたいものに払う。
つまり、納得したものに対してお金を払う事は当たり前のことだし、納得してもらう為の努力は、相手に媚びる事とはまた別の話しだと思います。
そして、どうせ同じ努力をするならば、どうすれば自分が思うような効果が出るか、ときには自分とは違う立場になって考えてみる事は、結局自分の為に良いことなんじゃないかとも思うのです。
うちの実家は数年前まで商いをしていたんですが、父が
『数字を扱う人間ばかりだと、会社も産業も潰れる』
と言っておりました。
この場合の数字は採算ではなく、目先の数字を追いかける事の意味で、開発や生産をないがしろにしたらダメという話しだと思います。
でも、なんだかんだ言って、計算してくれる人は大事だし、けど、そういった人たちや、生産者や開発者にもどうやったら良い塩梅かっていう考えが一つあれば、ない場合とは違う結果になるんじゃないかな?とも思います。