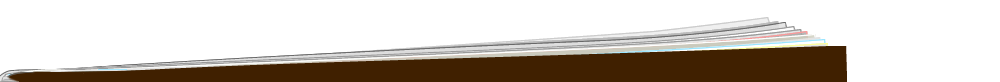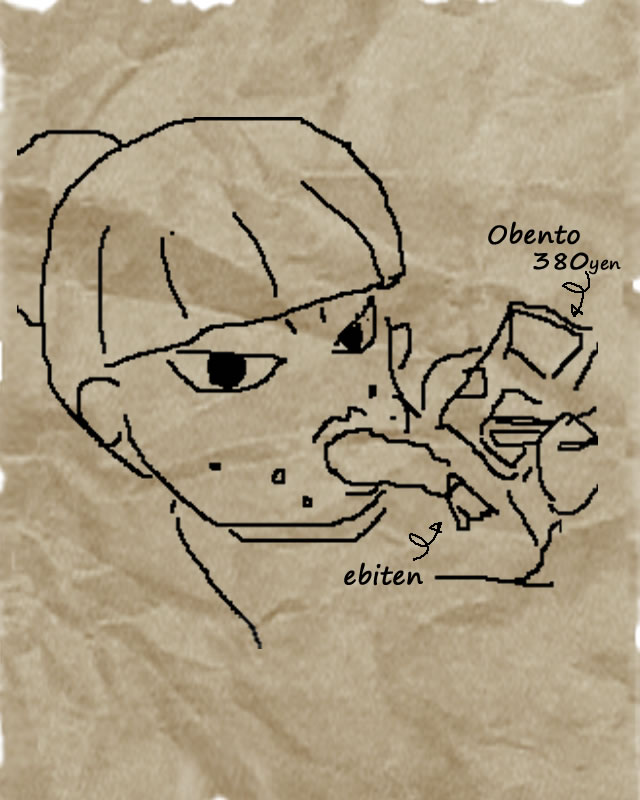脳の向こう側
私の指輪には『E=mc2』と刻印されています。
アインシュタインの相対性理論?まぁ、そうなんですが、
1979年のアメリカ映画にリトルロマンスという作品があります。ダイアンレインのデビュー作。
その映画の原作のラストで、小さな恋人たちが離れ離れにさせられるんですが、その時、少年が咄嗟にはじき出してプレゼントしたのが、アインシュタインと彼女への思いをかけた『E=mc2 (mon amour)』 愛しい人と言う意味です。
さて、話は指輪じゃなくて、アインシュタイン。
あのアインシュタインですら、人間の脳の10分の1程度しか使ってないと言われてますね。
…とすれば、私のようなあんぽんたんは、その何分の1か、何十分の1かっていう話しでしょう。
でも、それを駆使して、一生懸命考えごとしてみたり、悩んだり、まぁ…いろいろするわけですよ。
で、簡単に行き詰る。
私の場合、正しくは根気のなさとか、超ヘタレっていう事があるんですが、限界を感じるんです。
『もう、だめじゃ~~~』
みたいな。
でも、それって、脳の中の本のちょびっとの部分、ちんまい世界での話しですよね?
つまり、もし脳をフルに利用したのなら、また別の方法や、考えが浮かぶかもしれない。
と考えた場合、自分が感じている限界っていうのは、本当の限界ではないんじゃないか?と思うんです。
今の自分が、たまたまそれを見つけられない状況にあるって感じで、その枠の向こうには、違う考えや解決方法がゴロゴロしてるんじゃないかと。
ただ、慣性の法則を用いれば、同じ条件で同じ事をしていれば、同じ結果になるので、それにどっぷりつかってしまえば、それ以外の何かがあるとも思い難いだけで。
そんな事を10年ぐらい前から言っていたわけなんですが、それでもやっぱり行き詰る。
何が起きているかっていうと、
脳味噌っていうのは、記憶したり、考えたり、分析判断したり、発言や行動を決める機関ですよね?
と同時に、その人を守ろうとする機関でもあります。
例えば、気が赴くまま行動しようとすると、
『そんな事をしちゃ危ないよ』と注意したり、『ケダモノ』と言われないようにストップをかけてくれたり。
過去の経験や状況、情報を分析して、その人が壊れないようにコントロールしてくれるわけです。
ところが、人っていうのは感情っていうのがあります。これはこの上なく自由で、新しい事をぽんぽん生みだす存在。
感情をコントロールすると言いますが、実際にはコントロールすることはできないぐらい自由なんです。
が、それでは困ることもあるので、脳が感情をなだめたり、説得して、あまり自分の中で意識しないようにとしている状態。
で、それがうまく行けば、ヤレヤレってな感じで、そのままほったらかしておきます。
が、そうもいかないのが感情。
そうなると、ブレーキを踏みながら、アクセル全開みたいな状態になる。
そうなると、どうなるかっていうと、方向性を失ったり、壊れたり。どうして良いのかわからなくなったり、自分の気持ちがわからなくなったり。
脳の中に良くも悪くも過去の残骸がたくさんあります。
例えば、子供の頃、泣きわめけば大人が思い通りに動いてくれると感じた場合、この方法が使えないと自覚するまでは、その方法で問題解決をしようとするとか、根気や努力が実を結んだと実感する経験があれば、その後もそうあろうとしたり。
あれをしてはダメ、これをしてはダメ、怖い目に遭う。
こんな思いがたくさんあれば、やっぱり何かをする時躊躇ったり。
子供のころって、多かれ少なかれ大人が子供の行動を制限するもんなんですが、それが過剰で、子供の気持ちを抑え込んでしまうほどであれば、自分の行動に自分が主導権を持っていいと言う事がわからなかったり。
でも、上に書いた通り、所詮、記憶の残骸なのです。
このストッパーを克服しなければ!と思うと、よくわからない戦いが、脳の狭い部分でだらだら続くのです。
でも、それ以外の部分の世界の方が圧倒的に広いわけですよね?
だったら、戦い挑むより、脳を誘って、その向こうの世界を見に行った方が簡単なのかなあ…とも思うこのごろです。
良いんですよ。これから勉強したい事でも、他人の知恵でも、まだ見ぬ世界の景色でも何でも。
自分の脳の向こう側が何であっても構わない。
私みたいなできそこないは、まだ見ぬ世界が広すぎて、冒険し甲斐があるし、それだけ、可能性が転がってるとも言えるわけだし。
ただ、その前に、宿題をやらなきゃ。
今月までに、課題を2枚提出しなきゃならんのに、教本を開けた途端眠くなる。
ぶっちゃけ、ちょろいと舐めていましたが、そう簡単でもなく、それより何より、とにかく眠くて進まない。
冒険はその後の話しなのでしょう。