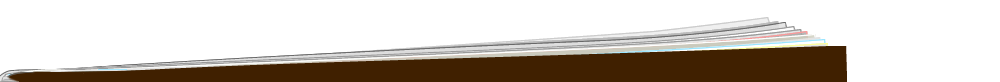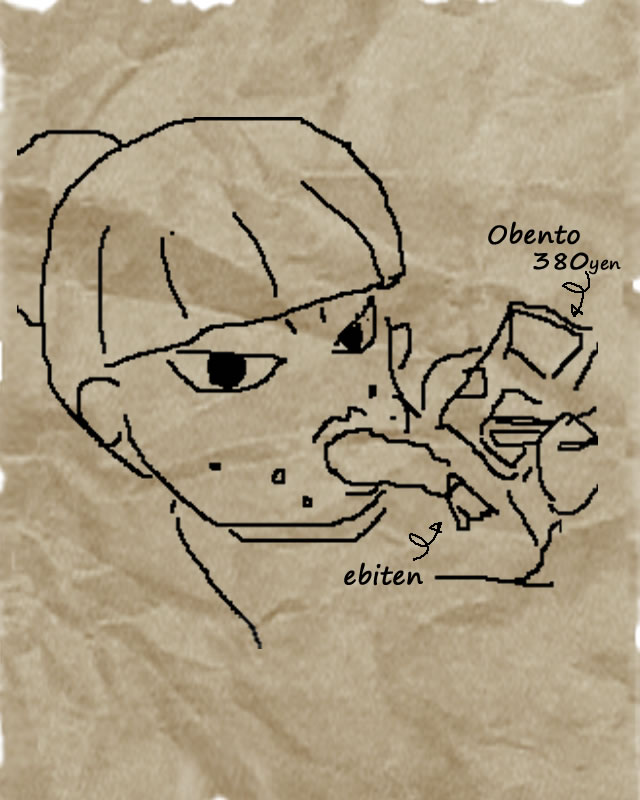呑み頃
いろんな作業ができずにモヤモヤ。
引越しを前提にプランターの土も捨ててしまったので、野菜も作れずモヤモヤ。
だからといって、お酒で憂さを晴らすようなことはしないのですが、楽しみの一つであるので、お酒の話。
基本的に、私は本醸造をのみません。
気がつかずに呑む事もありますが、頭が痛くなったり、悪酔いすることが多かったので、怖くてのめないのです。
勿論、本醸造の中にもおいしいお酒もあれば、本醸造に気づかずにのむこともあるのですが、とりあえずはそんな感じ。
なので、お燗と言えば本醸造が比較的多いのですが、私の場合は燗も純米酒で頂くことが多いのです。
といっても、燗酒を飲み始めたのはここ1年ぐらい。
それまでは、あのむわっとしたのがどうも嫌いで、敬遠しておりました。
が、お酒って体を冷やす食物なんですよね。その中でも日本酒は一番冷やしにくいわけですが、
二日酔いの日々の中で、体を温めると内臓への負担が軽減されて、二日酔いの症状が軽くなるというのがわかり、で、ぼちぼちと呑み始めたのです。
で、その燗酒。
昔、耳をもって『あちっ』とかいうCMがありましたが、私の中の燗酒のイメージっていうのも、そのCMの熱々だったり、もうひとつよく言われる人肌だったり。
ところが、実際にはそうじゃないんですよね。
お酒ごとに、呑み頃が違う。
お酒は薫酒(香りが高いお酒)、爽酒(軽やかなお酒)、醇酒(コクのあるお酒)、熟酒(古酒など)といった4つのパターンに分かれるようで、それぞれに適温の傾向が異なるといわれております。
ただ、実際に呑んだ感じでは、そんな風にぺキッと分かれてくれるようにも思えないんですが、
お酒ごとに、冷で頂くのが向いているお酒もあれば、常温や温めて頂くのが向いているお酒もあるって感じ。
その温度がまた微妙で、例えば、香りが高いお酒は、温めることによってその香りが台無しになるからしないものだといわれる事が多いのですが、香りを失う代わりに、酒の味が引き出されるなんてこともあるし、例えば、燗に向く酒といわれていたとしても、20度~50度までおいしいお酒もあれば、20~30,50度はおいしいけれど、40度はそうでもないっていうお酒もあったり。
冷酒の場合もそうです。ギンギンに冷やすのもまた良しというお酒もあれば、そうでもないお酒もある。
温度によって、香りや味が活きたり、引っ込んだり、変化するのが日本酒なのです。
勿論、呑む人の好みにも大きく左右されますが、そういった感じなので、温度によってでてくるお酒の性質っていうのは、頭で考えて温度を決めるより、飲み比べる方がよっぽど早いと私には思えるのです。
家では、ちょこっとずつ温度を変えて飲むことは可能ですが、お店で呑み頃にあたるかはまた別の問題。
お店のご主人次第になります。
おそらく、私が燗酒を嫌っていたのは、たまたま、苦手なタイプのお酒をむわっと出され続けたからでしょう。
もともとお酒をおいしいと思ったことがなかった私。
なので、ビールや日本酒のここが嫌いっていうのは、散々味わってきたと思うんですが、
それが覆るっていうのか、それこそ、自分のための一本を見つけるのが日本酒の醍醐味よって思えるぐらい、とにかく、すご~~~くいろんな味や香りやタイプがあるのが日本酒。
その1本の中でも、呑む温度によって味がいろいろに変化する。
そのことを、頭の隅にちょこんとあれば、もっと日本酒が楽しめるだろうし、お店でも気持ちよくお金を払うことができるんだけどなぁ…と思う昨今でございます。
これからは、すっと呑める様なタイプを冷たくしていただくことが多い季節になると思うんですが、梅雨寒の日もあるかもしれません。
燗をつけるといっても、熱いのだけが燗酒ではないので、いろんな温度を楽しめて貰えたらいいなと思います(^∇^)
上に書いたように、サボりがちではありましたが、サイトの更新もパソコンの都合でできませぬ。
しばしお待ちを。